top of page
明石市 裏千家 茶道教室
壺中庵、教室のご案内
お稽古環境を一部ご紹介。
季節に移ろう美しい庭を眺めながら
お稽古しませんか?
ぜひ一度見学しにいらしてください。

茶室「壺中庵」(四畳半 台目向切)
��大徳寺派第十二代管長、方谷浩明師の御命名である壺中とは、昔仙人が壷の中に住んでいたという故事から、茶道においても狭い茶室を時空を超えた妙境、別天地をあらわす仙境に見立てたものである。

瑞雲の間(三畳隅炉)

静修の間(八畳)

立礼好日の間(十八畳)

静遠の間(二畳中板)
静遠とは中国皇帝の御学問所についていた名前。
扁額の板材 金毛閣古材
扁額の墨跡 曹洞宗人丸山月照寺
間瀬碩禅師 昭和五十八年

大炉の間(六畳)

三重塔

待合 お腰掛

庭 能舞台
能楽の発表会などを毎年開催。

壺中庵建築材料の説明
一、茶室の床、天井板と点前座天井縁、点前座無目
重要文化財、紫野大徳寺塔頭興臨院は室町時代約四百五十年前能州大守畠山氏創建、後桃山期には前田利家公先祖菩提所と
為し、又茶道史上有名なる堺の今井宗久及び山ノ上宗二など共、縁故深き寺也。這回初めて昭和の大修後に際して是が古材を用いたものである。
二、向切小板、結界
紫野大徳寺山門、金毛閣は天正年間茶祖と謂る利休居士寄進、閣上には今も木像を祀る。先年解体修理その古材をもって右二点を作る。
昭和五十三年 興臨院 大癡老師
壺中庵の蹲石
岡山市足守町。最上本山龍泉寺霊山の御石にして壺中庵に縁あって、蹲を使用された方々の健康守護の御祈祷を龍泉寺嗣法、
最上日孝僧正から戴しものなり。

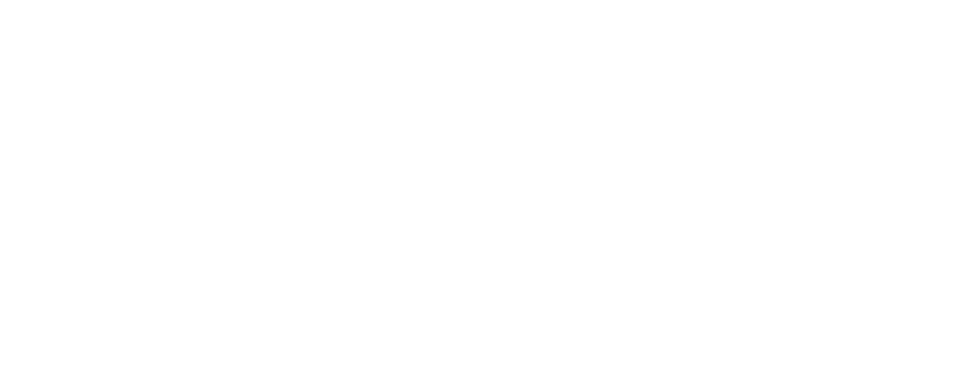
bottom of page